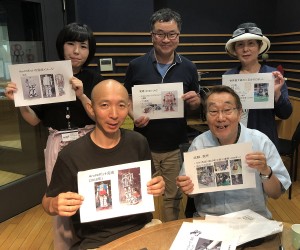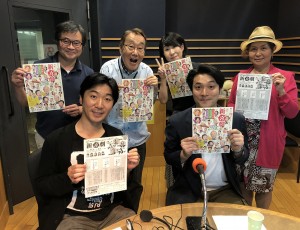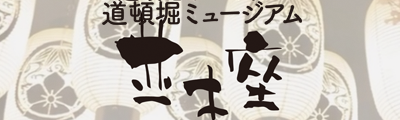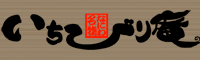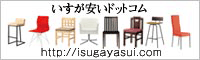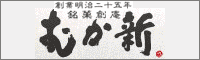今夜のお客さまは作曲家、音楽プロデューサーの松岳一輝さんです。
松岳一輝さんは1958年生まれ、兵庫県の出身。アーティスト、指導者、音楽ディレクターを経て、1988年から作曲家活動に。CM、企業イメージソング、イベント、皇室参加行事、舞台、番組音楽、アーティストへの楽曲提供など、幅広い分野で活躍され、手がけた楽曲は800曲を超えます。また、和と洋の融合をコンセプトに結成した自身のバンド「電気的祝祭楽団OTO-DAMA」で精力的に活動、これまでに2枚のアルバム、1枚のDVDを発表。歌劇界との交流も深く、OSK日本歌劇団、OSKOG、宝塚歌劇団OG,長崎ハウステンボス歌劇団、演劇集団などへの楽曲提供も積極的に取り組んでおられます。OSK日本歌劇団「春のおどり」は、2014年の「桜花昇ぼる退団記念公演」をはじめ2015年、2016年、そしてことし2018年の高世麻央退団記念公演。2010年、桜花昇ぼる主演「YUKIMURA・・・我が心炎の如く」、2015年、高世麻央主演、打打打団天鼓との「太鼓歌劇 ブラインド」、 桜花昇ぼる 鳴海じゅん 洋あおい 未央一らによる「大阪城パラディオン」、2017年、浪花人情紙風船団公演「不思議 な、な。」などなど、おとなの文化村でもご紹介してきた多くの公演の作曲・音楽担当を務めてこられました。 今夜は、来たる10月13日~14日 サンケイホールブリーゼで公演される、宝塚・OSKのOGによる「ジャンヌダルク ジュテームを君に」の紹介はもちろん、中学3年生の時、全国音楽コンクールに自作の曲をエントリーし、その曲が大賞を受賞・・翌年の春、一人故郷を離れ上京・・音楽の世界に入り30歳の時に作曲家として独立したその歩みもおうかがいしたいと思います。

これに関連する記事
今夜のお客様は「有限会社はじめ研究所」代表の坂本元(はじめ)さんです。
坂本はじめさんは1967年(昭和42年)和歌山県田辺市のお生まれ。1989年、上智大学理工学部電気電子工学科を卒業、川崎重工業に入社。2000年に退社され、2002年(平成14年) ヒューマノイドロボット、機械制御・ロボット制御システムの開発・製造を手掛ける「有限会社はじめ研究所」を設立されました。ROBO-ONE優勝、ロボカップ優勝、ロボットを提供したチームの優勝など数々の伝説を作り上げたヒューマノイドロボットの先駆者として、この世界では知らない人はいない存在です。高校時代「ガンダム」のプラモデルをきっかけにロボットの仕事がしたいという夢を追い続け、40センチのロボットからスタートいままで50種類・200体以上のロボットを製作した坂本さん、最終の夢はガンダム、18メートルロボット。今年、地元西淀川の町工場グループ「NKK」のプロジェクトリーダーとして、4メートルの2足歩行ロボットを完成されました。今夜はガンダムを目指す坂本さんの夢をたつぷりとお伺いしたいと思います。
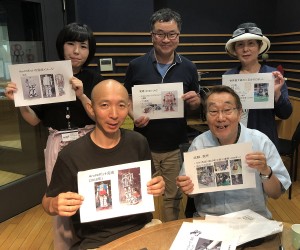
これに関連する記事
今夜のお客様はこのたび「劇団創立70周年記念公演」を開催することになった松竹新喜劇からお二人の若手をお迎えしました。
植栗芳樹さんは1981年・昭和56年、大阪府の出身。平成19年9月「松竹新喜劇」に入団、コミカルで元気な演技が特徴で、どんな役にも一生懸命にぶつかる姿勢で劇団以外の公演やテレビ、CMなど数多く挑戦されています。渋谷天笑さんは1984年・昭和59年、大分県の出身。平成22年4月「松竹新喜劇」に入団。胡蝶英治として活躍、昨年9月公演より二代目渋谷天笑を襲名。劇団きっての若手二枚目俳優として、舞台のみならず映像での活動も積極的に取り組んでおられます。来る9月3日から道頓堀松竹座で開幕する今公演では、人情喜劇の名作、茂林寺文福~曾我廼家十吾作の「人生双六」を、主人公宇田信吉役を藤山扇治郎さんが、その友人浜本啓一役を植栗さと天笑-さんがWキャストで演じることになっています。今夜は、次の時代を背負うフレッシュなお二人から見どころをはじめ、劇団設立70周年にかける思いなど、たっぷりと語っていただきましょう。
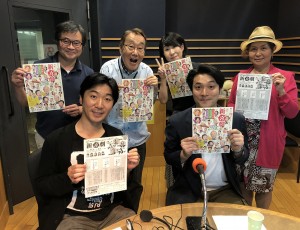
これに関連する記事